英国、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン・スポーツ健康研究所というところの研究論文からの抜粋です。(大元は「ヨーロピアン・ハート・ジャーナル」でメディカル・トリビューンの記事より)
結論を先に言うと「活動量の強度を少し増やすだけでも心臓の健康に良い影響を与えることが出来る」という至極最もだけれどなかなか出来ないという話題です。
5か国、1万5千人、平均53.7歳(±9.7歳)の「活動、座位、睡眠」の共同研究からデータを抽出し、5種類の身体活動(睡眠、座位行動、立位行動、低強度運動、中高強度運動)と
6種類の肥満度と血管代謝指標(BMI、ウェスト周囲、HDLコレステロール、総コレ-HDL比、中性脂肪、HbA1c)との関連を調べたものです。
太ももに装着するウェアラブルデバイスで1日の活動量を測定した対象者は、平均して睡眠に7.7時間、座位行動10.4時間、立位行動3.3時間、低強度運動に1.5時間、中高強度運動に1.3時間を費やしていました。
解析からは座位行動と比較して心臓の健康に最も良い影響をもたらすのは中高強度運動で、その次は低強度運動→立位行動→睡眠の順であることが明らかになっています。
心臓の健康に最も効果的なのは、たとえ数分でも座って過ごす時間をランニングや早歩きなどの心拍と呼吸数を上げるような中等度から高強度の運動に置き換えることなのです。
立っていることや眠っていることでさえ座っているよりは良いことが示されたということです。
また中高強度運動をすることにより、検討した肥満度、血液代謝指標のすべてが改善することも示されています。そりゃそうですよね。
低強度運動を中高強度運動に置き換えることでHbA1cが改善(は最小3.8分)から座位を中高強度運動に置き換えることで中性脂肪が改善する(のは最小12.7分)など幅がありました。
運動が心臓、血管の健康に効果があるのはすでに知られている事ではあると思いますが、毎日の生活の一部を少し置き換えること、そしてそれを継続して習慣化することで心筋梗塞や脳卒中の発症リスクを低下させられるということがこうした研究でも立証されているわけです。
しかし、健康という目的のために毎日を活動的に過ごすことは歳をとればとるほど容易なことではありません。
若い世代であれば日々の生活や仕事がそのまま運動になるのですが、現代生活では必要な身体活動も少なくなり中高年になればなるほど身体を動かそうというエネルギーもモチベーションも低下してきます。
しかし動物である以上、脳も筋肉も骨も血管も含め全ての臓器、組織に適度な刺激を与え続けなくてはいけないのです。
次回は座位と乳がんの関係の論文についてまとめたいと思います。
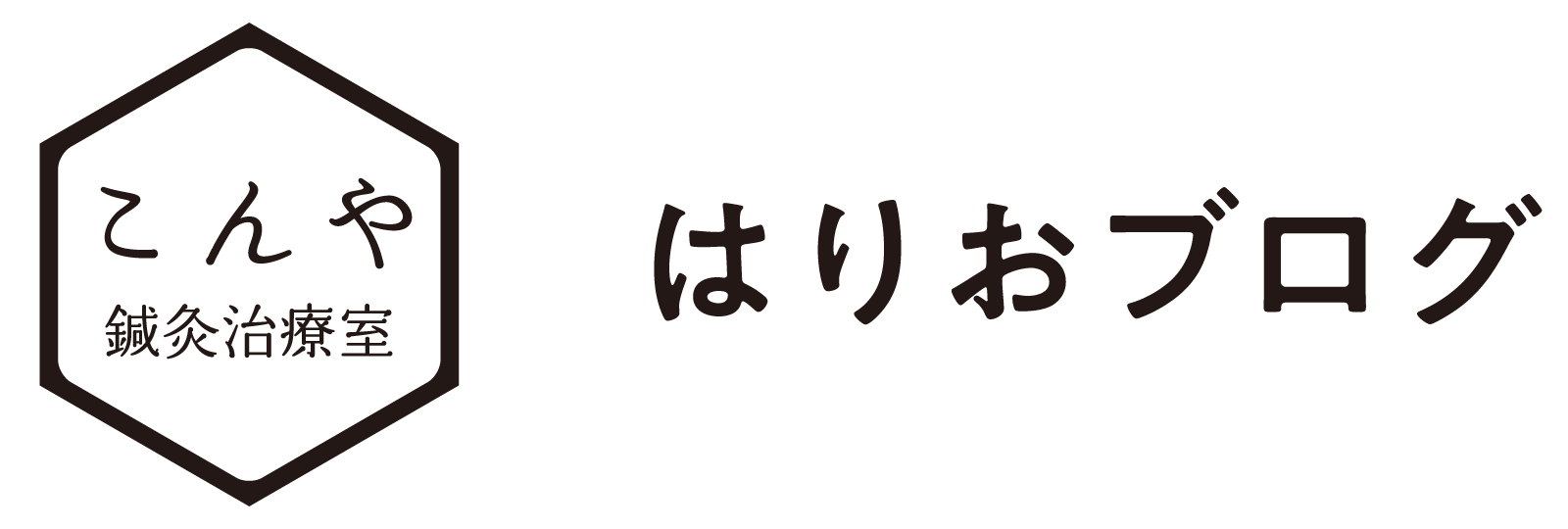



コメント