タイトルの言葉(これは金言!)はうつによる数度の自殺未遂から立ち直った小林エリコの著作から引用しました。(『わたしはなにも悪くない』 晶文社 )
90年代の鍼灸師としての修行中は三環系抗うつ薬という副作用もやや強めの薬しか処方されておらず、それで鍼灸院にも自律神経系の患者さんがとても多かったという印象、側面があります。
今世紀に入る頃から抗うつ薬の保険適用も増え同じくしてメンタルクリニック、心療内科などが急速に増えたため新しい抗うつ薬(SSRI、SNRI、NaSSA)もかなり手軽に手に入るようになりました。
それはそれで辛い現状を改善、緩和するためにはとても重要だとは思いますが薬物治療だけでそれをずっと続けるのかという問題もあります。
心療内科の治療の基本にあるのは仕事を含む生活環境や生活習慣など生活の見直しと、思考方法つまり考え方を見直すこと。
そしてそれを継続すること、継続できる環境、できる心の状態におくことにあります。
いくら次々といい薬ができても変わらない環境だったり弱った心、体のままではそれが難しいことは明らかです。
2020年頃からボルチオキセチン(商品名トリンテリックス、SSRI+セロトニン受容体調節)が処方されている患者さんを何人か見るようになりました。
新しい薬が出る度に話題になりある程度の患者さんに使われますが不思議なことにそこから改善し、減薬し、今はもう薬に頼らなくても大丈夫という患者さんが増えた感じがしないのもまた事実です。
これは職業上のバイアスが大いにかかっているからなのかもしれませんが。
原因の一つとして薬物治療と治療の両輪をなす認知療法、行動療法などのカウンセリングが圧倒的に足りていないことが挙げられます。
その理由は以前からも再三指摘されていましたが薬物療法に比べ圧倒的に手間とコストがかかるからです。
ウチの患者さんによると臨床心理士の30分のカウンセリングで4千円程度(3割負担)と言っていました。
この患者さんは前向きに自分の精神状態と対峙していたので自らカウンセリングに力を入れているクリニックを探し、且つ鍼灸治療もしているということです。
しかし、通常、精神的にも体力的にも疲弊している人にとっては抗うつ薬をもらいにクリニックへ行くのが精一杯かも知れません。
でも自分を変えられるのはやはり自分でしかありません。
今はやむを得ず抗うつ薬でも構いませんが持続可能と言えるでしょうか。
他に見直すところはないでしょうか。
何か体に無理をかけ続けていないでしょうか。心に無理を強いてはいないでしょうか。
そこを改善できる可能性を模索するためにも、薬物一辺倒の依存状態から脱却するためにも。
樺沢紫苑チャンネルなど精神科医や大愚和尚のYouTubeでもいいでしょう。
カウンセリングや鍼灸治療などの非薬物治療もいいでしょう。
試みていただきたいと考えています。
『近年、生きづらさを抱えた若者は心理カウンセラーに相談に乗ってもらうのではなく、精神科医や心療内科医に診断と薬の処方を求める傾向を強めている。
生き方を変えることで問題の解決を目指すより、感覚を操作することで問題の対処をはかりたい。そう願うのは自分の生き方を変えることを望まず、また、そもそもそれが可能だとも思えなくなっているからではないだろうか』
土井隆義 (筑波大教授、社会学者)
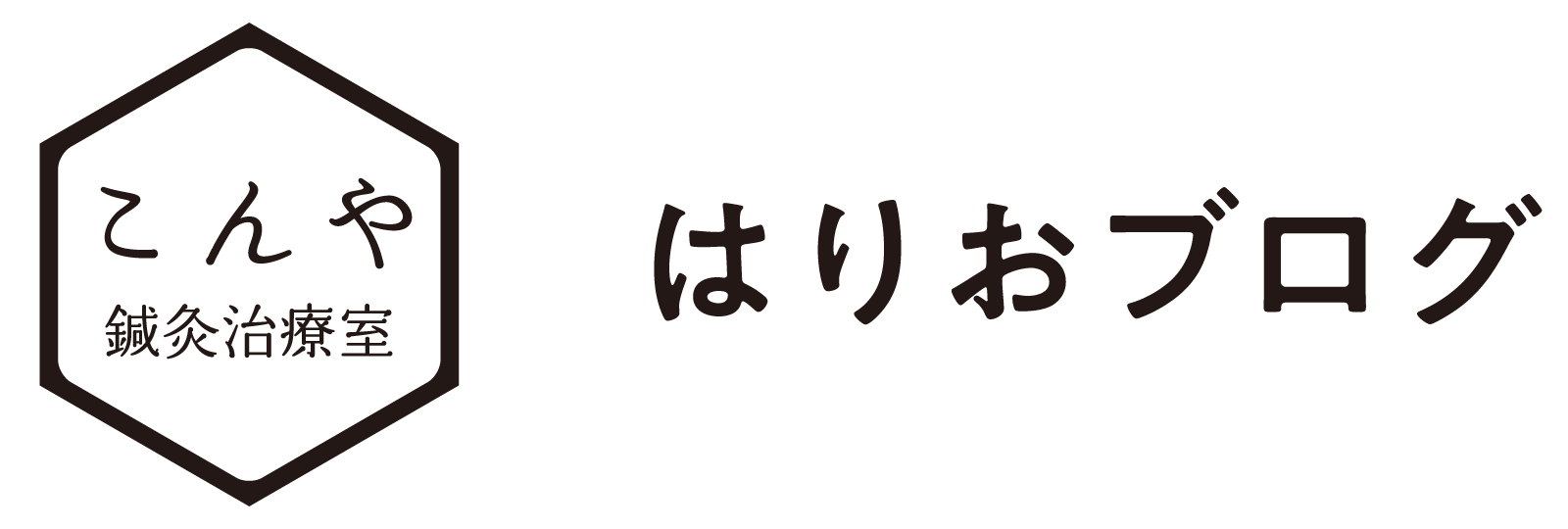



コメント